 |
| ●村の情報発信 ■ふるさと<■懐かしの福塩線> |
 |
| ●村の情報発信 ■ふるさと<■懐かしの福塩線> |
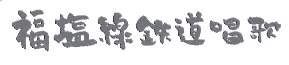 −沿線浪漫・JR福塩線を訪ねて− |
| 作 詞 : 田 口 清 人 |
| 市街を抜け田園を横切り山間を走りぬける福塩線。 福塩線は福山・塩町間を結び、私達の足として、暮らしをささえる一方、 昭和初期から現代までの歴史を静かに見守り続けています。 |
| 1. | 備南の雄都、福山の 其名も床し久松城 仰ぎて後に本庄へ つわものどもの夢の跡。 |
| 2. | 左に臨めば芦田川 九十九(ツヅラ)に曲がる山裾を 回(メグ)りて着けば飴の里、 横尾の笛の懐かしき。 |
| 3. | 福山街道、鶴ヶ橋 越ゆれば、開く古(イニシエ)に 穴の海とて知られたる 黄金(コガネ)の波の大沃野(ダイヨクヤ) |
| 4. | 高く聳(ソビ)ゆる黄葉山 夕日に映えて、山陽道 上り下りの旅人の 姿偲(シノ)ばす本陣や。 |
| 5. | 文人墨客相集(ボクキャクアイツド)ひ 備州の文化咲き競う。 今に続きし伝統か 此処(ココ) 神辺は文化の里。 |
| 6. | 湯田、道上、万能倉と 過ぎ行く彼方、 蛇円山(ジャエンザン) 発する泉堰(セキ)止めし 服部の池、 水蒼(アオ)く |
| 7. | 悲運のお糸物語り 老いたる松も咽(ムセ)び泣く 知らずや土手に咲く桜。 袖絞りつつ、駅家発つ。 |
| 8. | 近田の垰(タオ)の切通し 降(クダ)りし戸手の対岸は 備後絣の発祥地。 富田翁(トミタオキナ)の苦節あり |
| 9. | 蘇民将来(ソミンショウライ)の茅(カヤ)の輪に、 厄除け願う祇園社の 喧嘩神輿(ケンカミコシ)を眺めつつ 神谷川鉄橋渡りなば |
| 10. | 其の名も高き絣機(カスリバタ) 移ろう波に音絶えて いまやミシンの響く町 此処新市に降り立ちて |
| 11. | 備後の国は一の宮 併せて詣る桜山 建武の忠節偲びつつ 菊花の里を後にせん。 |
| 12. | 芦田の平野行尽きて 花の三宝の山裾に 開せし街は内陸の 工業都市や府中なり |
| 13. | 山紫に水清く 国府置かれし要(カナメ)の地 日本一の石燈篭。 進取の市勢示すなり。 |
| 14. | 面影淡し剣先の 水車の名残り椋の木を 遥かに眺め芦田川 渡れば備後嵐山。 |
| 15. | おおむらさきの里過ぎて 御調(ミツキ)川辺に滑り滝。 銀鱗(ギンリン)踊る渓流に、 沿ひて登れば河佐峡。 |
| 16. | 旗立原(ハタタチバラ)や衣装原(イショウバラ) 谷 堰上げし芦田湖は 昔 平家の公達(キンダチ)の 世に隠れ棲む伝説や |
| 17. | 一気に長きトンネルを 出づれ眩(マブ)し三川駅。 矢野の出湯はいと近く 旅の疲れを癒やすなん。 |
| 18. | 息せき切って登りり行く 翁(オキナ)の山の麓(フモト)なる 陰陽分ける要衝(ヨウショウ)は 昔、天領、 上下町。 |
| 19. | 石見の国の銀(シロガネ)を、 集めて強し其の力 今も白壁、 格子戸に 映すや古き夢の影。 |
| 20. | 甲奴、 安田と降り行く 小童(シチ)の祇園も指呼の間よ 鳥巣(トミシ)の富士の麗(ウル)ワしく 奥田元宋ゆかりの地 |
| 21. | 吉舎は文化の風薫る。 出雲分社を拝み見て 将棋の升田名人の 三良坂道を驀(マッシグ)ら。 |
| 22. | 馬洗の川の長堤(チョウテイ)に 沿ひて進めば見はるかす 彼方に赤き鉄橋は 芸備を結ぶ鉄路なり。 |
| 23. | 朝霧晴るる塩町の 駅舎に散るや花吹雪。 思ひは遠く八雲立つ 出雲の国に届けかし。 |
| 24. | 神杉、八次、三次駅 永き旅路も束の間に。 春は尾関の花を見む。 夏は鵜飼を楽しまむ。 |
(福塩線唱歌の著作は田口清人氏と青葉会に属す) −福塩線唱歌の掲載承諾済− |
|
| JR福塩線の歴史を沿線の街・人・自然と共にたどる思い出グラフティ。 ゆるやかな川面に沿って、山あいから田園地帯を抜け市街地へと走るJR福塩線。 80有余年の歴史を刻み、備後と備北を結ぶ重要な交通期間として、その役割を果たしてきました。 このビデオは、福山駅から塩町駅までの27駅沿線の歴史や街並みを福塩線鉄道唱歌の詩にそって紹介したものです。 (1997年9月編集)
|
| 2005/04/11 | 更新 |
| 1998/11/01 | open |
| ●村の情報発信 ■ふるさと<■懐かしの福塩線> |
 |
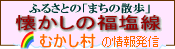 |
 |
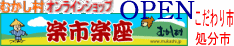 |